
会社設立サポート最短3日から対応!
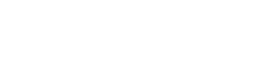

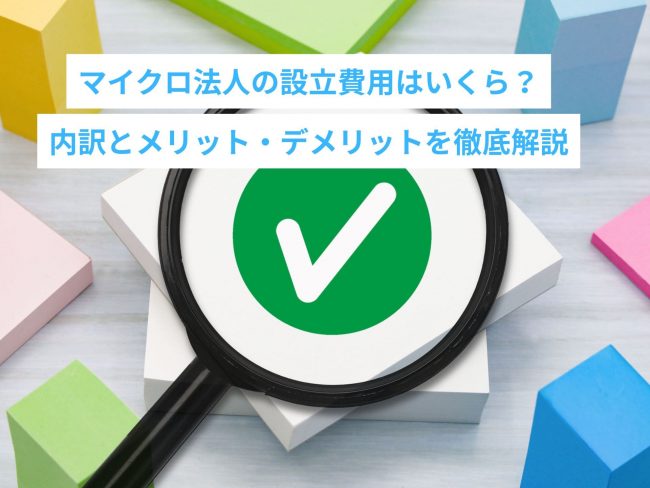
近年、フリーランスや副業をしている会社員の間で注目されているのが「マイクロ法人」の設立です。特に「節税対策」や「社会保険料の軽減」を目的として、個人事業主から法人化を検討する方が増えています。
しかし、マイクロ法人の設立にあたっては、どれくらいの費用がかかるのか、株式会社と合同会社では金額がどのように違うのか、本当に節税につながるのかなど、不安や疑問を感じる方も少なくありません。
この記事では、マイクロ法人を設立する際に必要な費用の内訳や、費用を抑える方法、設立にともなうメリット・デメリットをわかりやすく解説します。事前に知っておくことで、ムダな出費を避け、スムーズかつお得に法人化を進めることができます。
「マイクロ法人」とは、法律上の正式な用語ではありません。一般的には、代表者1人(または家族のみ)で運営される小規模な法人のことを指します。
フリーランスや個人事業主、副業を行う会社員の中には、節税対策や社会保険料の軽減、事業上の信用力向上を目的として、マイクロ法人を設立するケースが増えています。実際には、株式会社や合同会社など、通常の法人形態で設立されます。
たとえば、個人で業務委託などのビジネスを行っている場合、法人を設立することで、取引先との契約がスムーズになったり、経費計上の幅が広がったりするなどの利点があります。
また、法人化によって信用力が高まるため、融資や助成金の申請でも有利になるケースがあります。ただし、法人としての維持には費用や手間もかかるため、次の章ではその点について詳しく見ていきます。
マイクロ法人の設立には、個人事業では得られないさまざまなメリットがあります。特に節税や社会保険料の軽減を重視する方にとっては、法人化が有効な選択肢となることがあります。
個人事業主の場合、所得税は所得額が増えるほど税率が上がる累進課税となっています。一方、法人化すれば法人税率は一定で、利益が高いほど税率面で有利になることがあります。また、法人化後は会社名義で経費処理できる範囲が広がるため、手元に残る資金が増える可能性があります。
個人事業主は所得に応じて国民健康保険・国民年金の保険料が高くなる仕組みです。法人化し、代表者として自分に支払う役員報酬を適切に設定すれば、社会保険料の負担をコントロールすることができます。これにより、将来的な老後の保障を確保しながら、負担額を抑える工夫も可能です。
法人として登記することで、銀行口座の開設や融資の申請、助成金の申請、取引先との契約など、対外的な信用力が大きく向上します。特に「法人でないと契約できない」とされる取引先とのビジネスもスムーズに進めやすくなります。
新たに設立された法人は、一定の条件を満たせば最長で2年間、消費税の納税義務が免除されることがあります。これは消費税分の収入をそのまま利益として残せるという点で、大きなメリットとなる場合があります。
これらの理由から、収入規模がある程度あり、今後の事業成長を見込んでいる方にとって、マイクロ法人の設立はコスト以上にメリットが大きくなる可能性があります。
マイクロ法人には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットやリスクも存在します。設立前には、こうした側面を正しく理解しておくことが大切です。
法人は赤字であっても毎年「法人住民税の均等割(おおむね7万円前後)」が必ず発生します。また、決算ごとの申告業務や税理士報酬も発生するため、個人事業よりも年間維持コストが高くなります。収入が少ない場合や事業が軌道に乗っていない段階では、負担に感じることもあるでしょう。
法人を設立すると、定款の作成、登記、決算報告、各種届出などの事務作業が必須になります。これらは専門的な知識を要することも多く、個人事業に比べて手間や管理コストが増える点は否めません。特に初めて法人運営を行う方にとっては、思った以上に手続きの煩雑さを感じることがあります。
会社員が副業としてマイクロ法人を設立する場合、勤務先の就業規則に抵触する可能性があります。副業を禁止している企業もあるため、事前に確認しておかないと懲戒処分の対象となる恐れもあります。また、法人運営に時間や労力がかかることで、本業に悪影響を及ぼすリスクも無視できません。
マイクロ法人による節税は、一定の収益規模があることを前提としています。もし利益が少ない場合には、法人化による税率の優位性よりも、維持費や手間の負担が上回ってしまうこともあります。特に年間所得が数百万円未満の場合は、個人事業のままの方がコスト面で有利な場合もあるため、慎重な判断が必要です。
このように、マイクロ法人にはコスト面・手続き面・法的リスク面のデメリットが存在します。設立前にこれらを把握し、自分の状況に照らしてメリットと天秤にかけて判断することが重要です。
マイクロ法人の設立には、法人形態や手続き方法によって異なる費用が発生します。ここでは代表的な「株式会社」と「合同会社」それぞれの設立費用について、内訳を分かりやすくご紹介します。
合計すると、おおよそ20万円~25万円程度が株式会社設立に必要な初期費用の目安となります。
合同会社の場合は、電子定款を活用すれば約6万円~7万円程度で設立できるため、初期コストを大幅に抑えることが可能です。
株式会社・合同会社のいずれでも、電子定款を使用することで「収入印紙代4万円」を節約できます。電子定款の作成には専門的な設備や知識が必要なため、設立代行業者や行政書士に依頼するケースが一般的です。代行サービスの中には、設立手数料無料で電子定款対応をしてくれる業者もあるため、うまく活用することで費用を抑えられます。
このように、マイクロ法人の設立費用は10万円未満から25万円程度まで幅がありますが、会社形態や手続き方法の選び方次第でコストを最適化することが可能です。
マイクロ法人の設立には一定の費用がかかりますが、工夫次第でコストを抑えることが可能です。ここでは、代表的な節約・削減方法を紹介します。
電子定款を利用すれば、定款に貼る収入印紙代4万円が不要になります。紙の定款では必須となるこの印紙代を削減できるのは、大きな節約効果です。
電子定款は自力で作成・提出も可能ですが、専用ソフトや電子署名が必要なため、多くの方は行政書士や設立代行業者に依頼しています。手数料がかかる場合もありますが、印紙代4万円の削減効果の方が大きいケースがほとんどです。
コスト重視であれば、株式会社ではなく合同会社を選ぶという選択肢もあります。合同会社は、定款認証が不要で、その分設立費用を大幅に抑えることが可能初期費用を抑えたい方にとって現実的な選択です。
会社設立を無料で代行してくれる事務所やサービスを活用すれば、手続きにかかる人的コストや手間を削減できます。たとえば、当サイトでも紹介しているような「設立手数料0円」の会社設立代行を利用すれば、実費のみで法人設立が完了します。
また、設立後に顧問契約や創業融資の支援までワンストップで対応しているところも多く、長期的な経営支援も期待できるのがポイントです。
登記書類や定款に不備があると、再提出による時間やコストのロスが発生します。あらかじめ必要な情報を正確に整理し、専門家のサポートを受けながら進めることが、結果的に余計な出費を防ぐことにつながります。
このように、電子定款の活用・合同会社の選択・無料の設立代行サービスの活用といった工夫を行うことで、マイクロ法人の設立費用は抑えることができます。初期費用を理由に法人化を諦めるのではなく、賢くコストダウンして設立する方法を検討することが重要です。
法律上は、会社員が副業として法人を設立することに問題はありません。ただし、勤務先が就業規則で副業を禁止している場合は、事前に確認が必要です。副業の許可が出ている場合でも、本業に支障をきたさないように注意しながら、業務を分けて管理することが望まれます。
節税効果は所得の規模や経費の状況によって異なります。一般的には、年間の所得が800万円以上ある場合に法人化による節税効果が高くなる傾向があります。法人税の方が累進課税の個人事業よりも税率が低いためです。とはいえ、法人住民税などの固定コストもあるため、節税目的だけでなく、事業計画全体を見据えて判断することが重要です。
はい、マイクロ法人でも創業融資を受けることは可能です。日本政策金融公庫などでは、法人設立後すぐのタイミングで創業計画書や資金計画などを整えて申し込むことで融資対象になります。個人事業よりも法人の方が「事業としての信頼性が高い」と評価されやすいため、しっかりとした準備をすれば、融資を受けられる可能性は十分にあります。
法人を設立した場合、個人事業とは異なり「法人税の申告」が必要になります。通常は決算終了から2か月以内に法人税の申告書を提出する義務があります。また、給与支払いや源泉徴収、年末調整などの対応も必要になるため、税理士にサポートを依頼するケースが一般的です。
はい、可能です。マイクロ法人では複数の事業目的を定款に記載しておけば、ひとつの法人で複数の事業を運営することが可能です。ただし、事業ごとに会計処理を分けて管理することが望ましく、税務上のトラブルを避けるためにも収支の記録や口座管理は丁寧に行う必要があります。
マイクロ法人は、フリーランスや副業会社員、個人事業主にとって節税や信用力向上といった多くのメリットがある制度です。特に収入規模が大きくなってきた方や、取引先との信頼関係を強化したい方にとって、有力な選択肢となります。
一方で、設立や維持に一定のコストがかかることや、法人としての事務手続きの煩雑さなどのデメリットもあるため、事前に十分な検討が必要です。
株式会社か合同会社か、電子定款を使うか、代行業者を利用するかなど、選択肢によって設立費用は大きく変わります。コストを抑えながらも、安心して法人運営をスタートするには、専門家のアドバイスを受けることが非常に有効です。
もし、「マイクロ法人を作るべきか迷っている」「費用や手続きに不安がある」と感じている方は、一度プロに相談して、自分に合った形を見つけることをおすすめします。
マイクロ法人の設立には、正確な手続きと費用の把握、そして自身に合った形態の選択が欠かせません。とはいえ、初めての法人設立では「何から始めればよいのか分からない」「手続きを間違えたらどうしよう」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは、会社設立の無料相談を随時受け付けております。設立代行サービス(手数料0円)や創業融資のサポート、さらに設立後の税務顧問契約まで、あなたのビジネス立ち上げをトータルでサポートいたします。
「費用をできるだけ抑えたい」「自分に株式会社と合同会社どちらが向いているか知りたい」など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。