
会社設立サポート最短3日から対応!
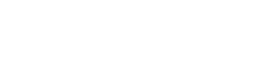

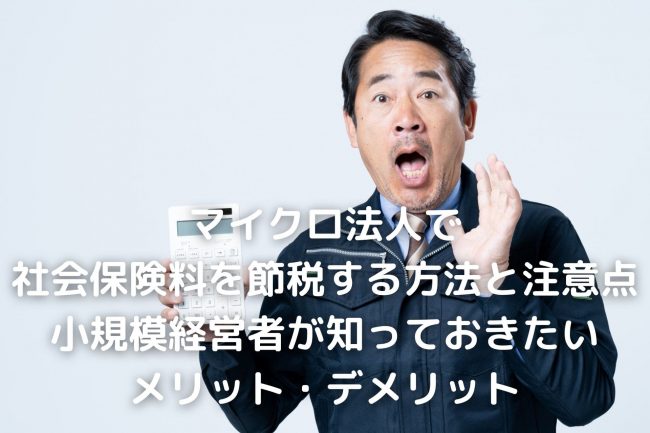
フリーランスや個人事業主として活動している方の中には、毎月の社会保険料負担が重く感じられるという方も多いのではないでしょうか。特に、所得が増えるにつれて国民健康保険料や国民年金の負担が大きくなり、節税の工夫が必要と感じる場面が増えてきます。
そこで近年注目されているのが「マイクロ法人」の活用による社会保険料の節税です。マイクロ法人とは、役員1名のみ、あるいはごく少人数で運営される小規模な法人のことを指し、主に個人事業主や副業・兼業の方が税金や保険料の最適化を目的として設立するケースが増えています。
この仕組みを上手に活用すれば、役員報酬の金額を調整することで社会保険料の負担を軽減できる可能性があります。ただし、誤った方法で運用すると、思わぬペナルティやトラブルにつながるリスクもあるため、正しい知識と準備が欠かせません。
この記事では、マイクロ法人を活用して社会保険料を節税する仕組みやそのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。マイクロ法人の設立を検討されている方や、社会保険料の見直しを考えている方にとって、参考になる情報をお届けします。
マイクロ法人とは、役員1名もしくはごく少人数で構成される小規模な法人を指します。従業員を雇わず、代表者自身がほとんどの業務を担うケースが多く、一般的な中小企業とは異なり、事業規模を最小限に抑えた経営スタイルが特徴です。
フリーランスや個人事業主、副業をしている会社員の方が、節税や社会保険料の負担軽減を目的として法人化する際に選ばれることが多いのが、この「マイクロ法人」という形態です。法人設立により、個人と法人の所得を分散させることが可能となり、税金面や保険料面で一定のメリットが期待できます。
ただし、マイクロ法人は正式な法令上の分類ではなく、あくまでも通称であり、株式会社や合同会社などの法人格を持ったうえで、その運用形態が“マイクロ”であるということになります。
マイクロ法人が近年注目を集めている理由の一つに、社会保険料や税金の負担が年々増加している現状があります。特に、国民健康保険や国民年金に加入している個人事業主は、所得に応じた保険料を支払う仕組みになっているため、所得が高くなるほど保険料も高額になってしまうという課題があります。
そのため、「所得を法人と個人に分ける」という手法を用いることで、所得税・住民税・社会保険料の合計負担を抑えることが可能となります。これが、マイクロ法人が節税対策の一環として活用される大きな理由です。
また、マイクロ法人を設立することで、法人名義の口座開設・クレジットカード作成・契約書締結が可能になり、ビジネス上の信用力も高まるという副次的なメリットも得られます。
マイクロ法人を設立する最大の目的の一つが、社会保険料の負担軽減です。個人事業主やフリーランスとして活動している場合、国民健康保険や国民年金に加入する必要があり、所得に応じて保険料が高額になる傾向があります。
一方、法人を設立し、自分自身を役員として雇用する形にすることで、健康保険と厚生年金(いわゆる社会保険)へ加入する形に切り替わります。この際の社会保険料は、役員報酬額に基づいて計算されるため、報酬の設定を工夫することで、負担を大きく抑えることが可能になります。
個人事業主の保険料は、前年の所得金額をベースに計算されます。所得が高くなるほど保険料も比例して上がるため、所得が不安定な年でも高額な負担が発生することがあります。
対して、法人化すると厚生年金・健康保険への強制加入「役員報酬」の額に応じて算出されます。つまり、報酬を低めに設定することで、社会保険料の負担も最小限に抑えることができます。
たとえば、毎月の役員報酬を88,000円(令和6年度の最低等級)に設定した場合、厚生年金と健康保険の保険料はおおよそ月額2~3万円程度に抑えることが可能です。これにより、年間で数十万円の保険料節約につながるケースもあります。
ただし、あまりに低い報酬設定にすると、将来的な年金受給額が減少するリスクや、生活資金不足の問題が生じることもあるため、無理のない報酬設定と事業計画のバランスが重要です。
マイクロ法人には社会保険料の節税や税務上のメリットがある一方で、設立や運用に伴うコストやリスクも存在します。これらを十分に理解したうえで検討しなければ、想定外の出費や手間に悩まされる可能性があります。
ここでは、マイクロ法人設立前に押さえておきたい主なデメリットとリスクについて解説します。
マイクロ法人であっても、法人を設立した時点で、たとえ代表者1名でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じます。これは法律で定められたものであり、任意加入ではありません。
よく「報酬が少ないから加入しなくてもよいのでは?」と誤解されることがありますが、報酬の有無にかかわらず、法人役員は原則として社会保険に加入しなければなりません。未加入のまま放置していると、後日遡って加入を求められ、高額な保険料を請求されるリスクもあります。
マイクロ法人の設立には、登録免許税や定款認証料など、少なくとも20万円前後の初期費用がかかります。さらに、法人を維持するには以下のようなコストも発生します。
これらの費用が、節税で得られる金額を上回る場合、結果的に法人化によって支出が増えるという事態にもなりかねません。
個人事業主に比べて、法人の運営には多くの事務手続きが必要です。たとえば、以下のような業務が定期的に発生します。
これらの作業をすべて自力で行うのは難しく、税理士や社会保険労務士などの専門家のサポートを受けるケースが多くなります。その結果、顧問料などの固定コストが発生する点も念頭に置く必要があります。
マイクロ法人の設立には多くのメリットがありますが、すべての人にとって最適な選択とは限りません。事業の規模や収入状況、今後の展望によっては、法人化がかえって負担になるケースもあります。
ここでは、マイクロ法人化に向いている人・向いていない人の特徴を具体的に解説します。
特に、年間所得が500万円を超えており、かつ社会保険料が高額になっているようなケースでは、マイクロ法人化による節税メリットが非常に大きくなります。また、事業を拡大する計画がある場合や、取引先の信用力を高めたい場合にも、法人化は効果的です。
マイクロ法人を維持するには、最低でも法人住民税や社会保険料の支払いが毎年発生します。これらの費用をまかなえない場合、個人事業主のままでいた方が合理的なこともあります。
また、事業が軌道に乗っていない段階で法人化すると、税務申告や帳簿管理の負担だけが増えるリスクもあります。法人化を検討する際は、現在の事業規模と今後の見通しを冷静に評価することが大切です。
マイクロ法人を活用した節税を実現するためには、正しい手順で法人を設立し、必要な届出や手続きを確実に行うことが重要です。ここでは、会社設立から社会保険手続きまでの基本的な流れを解説します。
法人設立の第一歩は、会社の基本ルールを定めた「定款」の作成です。定款には以下のような項目を記載します。
作成した定款は、公証役場で「定款認証」を受ける必要があります(株式会社の場合)。合同会社であれば認証は不要です。
この段階で注意すべきなのは、事業目的を広めに設定しておくことです。目的が狭すぎると、後に事業拡大をする際に再度定款を変更・登記する手間が発生します。
定款認証後は、以下の書類を作成し、法務局に登記申請を行います。
登記が完了すれば、晴れて法人設立が完了します。設立日は、登記申請を行った日が基準となります。
この段階で、会社の印鑑作成・法人用の銀行口座開設も並行して行うとスムーズです。
法人を設立した後は、以下のような税務署や関係機関への届出が必要になります。
また、社会保険については、年金事務所への「健康保険・厚生年金保険新規適用届」や「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。役員報酬を支払う月の前月までに手続きを行うのが原則です。
これらの届出は、期限を過ぎるとペナルティや保険料の遡及適用が生じる可能性があるため、早めに対応することが重要です。
マイクロ法人を使った社会保険料の節約は、役員報酬の設定次第で大きな効果が見込めます。ここでは、実際にどの程度の節税が可能になるのか、シミュレーションを交えて具体的に解説します。
あるフリーランスの方が、年間800万円の売上(経費除外)を上げているとします。個人事業主として活動していた場合、所得税・住民税に加え、国民健康保険料と国民年金を合わせると年間で約100万円以上の社会保険料を支払うケースも珍しくありません。
ここで、マイクロ法人を設立し、役員報酬を月額88,000円(年額1,056,000円)に設定するとどうなるかを見てみましょう。
結果として、国民健康保険と国民年金で100万円以上かかっていた社会保険料が、約33万円程度に抑えられることになります。
加えて、法人側が社会保険料の半分を負担することで、法人経費として計上できるため、法人税の節税にもつながるという利点があります。
このような節税は魅力的に映りますが、以下の点には注意が必要です。
したがって、節税だけを目的に法人化するのではなく、生活設計や事業計画とバランスを取りながら判断することが重要です。
マイクロ法人の設立や社会保険に関する手続きについては、初めての方にとって不明点が多く、疑問や不安を感じやすい部分です。ここでは、実際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
法人の代表者となった場合、国民健康保険ではなく健康保険(協会けんぽなど)への加入義務が発生します。これは強制加入であり、報酬の有無に関係なく適用される点に注意が必要です。
なお、副業としてマイクロ法人を設立する方で、本業で厚生年金と健康保険に加入している場合は、ダブルワークの取り扱いとなり、役員報酬の額や勤務実態によって社会保険の加入要否が判断されます。
マイクロ法人でも、家族を従業員や役員として雇用することは可能です。この場合、支払う給与は法人の経費として計上できるため、所得の分散や節税効果が期待できます。
ただし、実態のない勤務や名義だけの役員報酬は税務上問題となる可能性があるため、業務内容・報酬額・勤務実態をしっかり整備しておく必要があります。
また、健康保険の扶養関係の見直しも必要になるため、事前に社会保険の担当窓口に確認することが推奨されます。
事業の中断や廃止を検討している場合は、法人を「休眠(事業停止)」という形で存続させることが可能です。休眠届を提出すれば、営業活動を止めた状態で法人を維持できます。
ただし、社会保険については、役員報酬の支払いがなければ脱退可能なケースもありますが、事前に年金事務所に相談することが重要です。また、休眠中でも法人住民税の均等割や、税務署への申告義務(ゼロ申告)は継続されるため、完全に手間がゼロになるわけではない点に注意が必要です。
マイクロ法人を活用した社会保険料の節税には、多くのメリットがある一方で、設立手続きや社会保険の届け出、税務処理など専門的な知識が求められる場面も多くあります。
「自分のケースでもマイクロ法人化が本当に有効なのか知りたい」「設立や手続きに不安がある」「節税効果を具体的にシミュレーションしてみたい」――このような方は、専門家による無料相談をぜひご活用ください。
名古屋で会社設立サポートを行う税理士法人伊勢山会計では、法人設立から社会保険・税務手続きまでワンストップで支援しています。ご相談いただければ、お客様の状況に応じた最適な設立・節税プランをご提案いたします。
ご相談は完全無料・オンライン対応も可能です。
マイクロ法人の設立に関心のある方は、今すぐこちらからお問い合わせください。